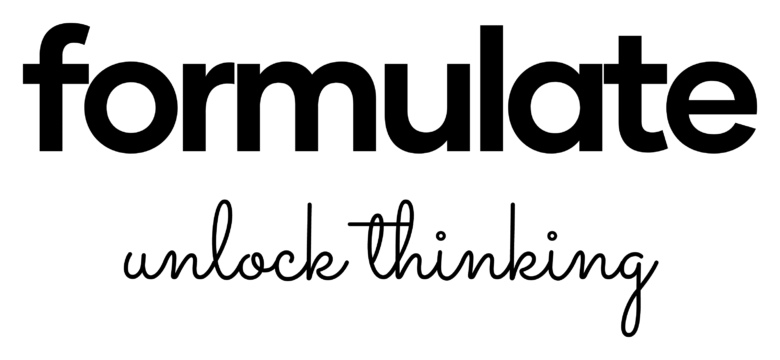会議を効果的に行う方法としてよく挙げられるのが、目的を設定する、アジェンダを決めておく、資料を先に読んできてもらうなどがありますが、より話し合いがしやすくする3つのポイントを紹介します。
今回は2つ目の紙ざらに載せる、です。
話し合いは難しい、を前提に
話し合いをしましょう、と何気なく奨励しますが、そもそも話し合いは人にとって難しいものです。
特に、アジアの文化圏では周囲がどう思っているかが自分の気持ちを定めている、という社会心理学の調査結果もあります。人の意見を聞いてから、自分の意見を決める人がいるのは文化的な特徴なのです。
この特性を活かしつつ、話し合いやすくするためのポイントが操作性です。
紙ざらを載せて話し合う方法
会議を変える①で紹介したポストイットを事前に書いておきます。
紙ざらに載せる
- 100キンなどで売っている紙皿を30枚くらい用意します
- テーブルにいくつかの山にして置いておきます
- 書いたポストイットを紙ざらに載せます
テーブルに配置する
- ポストイットを載せた紙皿をテーブルに配置します
- 主催者は、テーブルの辺に意味を持たせます
- 例えば、窓側の辺を最も難易が高い、手前が容易にできそう、と設定します
- それぞれ、思う位置に自分のポストイットを配置します

* 自分が思う位置に紙皿を配置します。他の人の意見の紙皿は、勝手に動かさない約束にしておきます。
期待できる効果
全員の意見がテーブルに上にのることで、参加者の当事者意識が高まり、話し合いが活性化します。
紙ざらは簡単に動かせるため、それまでの固定化された概念がはずれ、他のメンバーと一緒に「出来そう」なマインドセットで話し合いを進められます。
また、紙ざらを置いた人は、その位置について他の人に意見を求めることも出来るので、不安になることなく自分の位置(意見)を決められます。
ニューロサイエンス
脳は、脅威か報酬のいずれかのモードに反応します。
話し合いの時は、報酬モードにすることで、脳の働きがよくなります。

紙ざらは自分で動かせるため、報酬を感じる「自己選択感」が得られます。
自分で動かせることで、思っていた事象や課題はどうにもならない事ではないと思えるのです。
参考文献:
Between Us: How Cultures Create Emotions by Batja Mesquita
『SCARF® in 2012: updating the social neuroscience of collaborating with others』(2012, Dr. David Rock and Christine Cox, Ph.D)
Photo by Markus Spiske on Unsplash